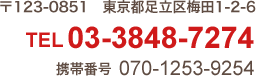Q&Aコーナー
- HOME
- Q&Aコーナー
前書き
大雑把に申し上げますと「療育塾ドリームタイム」に来られる子どもたちの内
・約3割は知的障害をともなう「自閉症」の子どもたち
・次の3割は通常学校に通いながらも様々な困難を抱えている「ADHD」や「アスペルガー症候群」の子どもたち
・さらに次の約3割が「知的発達障害」や「ダウン症」といった子どもたち
・残りの約1割が「脳性麻痺」や重度の「運動発達遅滞」と言われる子どもたちです。
中にはお医者さんの誤診と思われるケースもありますが、傾向としては上記のとおりです。
ここで登場する数々のご質問は、その中でも頻度が多かったご質問を主に取り上げてみました。
(A)お子様の生い立ちに始まる今までの発育・発達の詳しい経過(時間軸の情報)
(B)診断名や合併症など
(C)テーマとなる状態像がいつ頃から生じ始め今に至っているのか(時間軸の情報)
(D)テーマとなる状態像がどの場所(家・園・学校など)で生じやすいか(空間軸の情報)
(E)テーマとなる状態像が関わる人によっての違いがあるのか(対人関係軸の情報)
(F)テーマとなる状態像が環境の変化や気候の変動の影響はあるのか(状況軸の情報)
といった数々の「情報」を抜きには、本来は語れないものです。
ですので、このページでは「一般的=平均的に想定される状態」を手がかりにお答えしていることの限界がある=「必ずしも我が子には当てはまらない可能性もあり」ということを ご了解の上、お読みいただければと存じます。
主として「××をしでかす(問題行動と言われやすい)」ことについて
Q1. 発達していく中で、「自傷」から「他害」に行動が変化していった自閉症児のこと
5歳になる自閉症の息子を育てています。週2回、地元の発達センターでのグループ療育にも通わせていますが、いまだに言葉は[アィー(イエスの意味らしい)]や[ウゥー(飲み物が欲しいとき)]程度しかなく、要求表現の殆どはクレーンです。
3歳児から通っているのでずいぶんと発達センターの指導にも慣れてきたようで、グループ活動の流れには逆らわなくなってきました。しかし、年長(5歳児)クラスになってから、クラスの子を叩いたり噛み付いたりするようになってきました。担任の先生(保育士)も、その都度息子の目を見ながら「やってはだめです!」と強く叱ってもらってはいるのですが言うことをききません。どうしていったらよいのでしょうか?
A1.他者に対して行う 叩く・突き飛ばす・咬みつく といった行為は一般的には 他害と呼ばれるものです。ご質問にお答えするにあたっては、これだけの情報だけではズレたアドバイスになってしまう可能性があるので、押さえておかなければならない情報が大きく分けて3ポイントあるのでそこから説明していきたいと思います。
- 1つ目は「なぜ、今までは他害が出なかったのか?」です。おそらく、他害にたどり着くまでの前段階(≒前駆症状)があって、そこが見過ごされてきた可能性が大です。
- 2つ目は「ご家族に対しては、あるいは関わる大人たちには他害はなかったのか?」という情報です。これはお子様が「人との関わり」をどの程度発達させてきているかを判断するための重要情報です。
- 3つ目が「他害に陥りやすい時期や環境条件、状況はあるのか?」という情報です。
これらのことを親御さんから伺っていったことで、いくつかのことがわかってきました。
1つ目については、「他害」の前には「自傷」が激しかったという事実です。今までは思い通りにならなかったときに、自分の顔や頭を叩く・自分の手や腕を咬みつくという「自傷」が頻繁に見られたとのことでした(時間軸の情報)。
2つ目は、穏やかな若い女の先生や、家では母に限っての「他害」が出ているようです。どうも「返り討ち(?)に合わない相手」に対して叩いたり咬みついたりしているようです。家でも父親や空手を習っている小4の兄に対してはほとんどやらないこともわかってきました(空間軸と対人関係軸の情報)。
3つ目は行事の前になると、かつては「自傷」が、今は「他害」が多く出る。および天候が悪いとき、特に台風が近づいてきているときには顕著に出ることもわかってきました(状況軸の情報)。
ここまでの「情報」が集まってきたことと、「知的障害をともなう自閉症」のお子さんがたどりやすい発達のつまずきを知っていると、次の2点が原因および要因として見えてきます。
- ひとつは、自傷が始まった頃は、自分の「思い通りにならない事態」で、他害が出始めた頃には「このあと何が起こるかの見通しが持てない」時というお子様の知的な能力(専門的には「表象機能」といいます)の未発達さが、情緒的な不安さを作り出してきたであろうことが容易に察せられます。
- もし、お子様に自閉という症状がない健常児だったとしたら、同様のことは2歳前後から見られ始めたでしょう。そして、親(や身近な親しい大人)との「心の絆」があれば”自然に”治まっていったでしょう。いわゆる「イヤイヤ期」の様相です。情緒的な不安定さが生じたとしても、その思いを共有してくれる大人との共感性やその土台となる愛着形成(=アタッチメント)があれば、その相手を心の依りどころとして気持ちを落ち着かせていくのが健常児の姿です。しかしお子様は自閉性があるためにここの土台を形作って行くことが困難でした。
※ただし愛着形成のつまずきについて「親には責任はない!」ことだけは明言しておきたいと思います。むしろ、愛着の発達を阻害しないような子育てのアドバイスを専門家がしていくべきだったでしょう。
結果的に、思い通りにならなかったときに湧いてくる憤りには「自傷」で、わずかながらも伸びてきた「相手との力関係(対人関係)が見えてきた」結果として、最近では「見通しが立たない不安」に陥ったときには八つ当たり的な「他害」をするようになったのではないか?と推察されるのです。
A2.そこで、まず対処してあげられる対策として、以下の方針が必要でしょう。
- AAC(拡大代替コミュニケーション)の活用
お子様にとっては、まだ自分の思いを音声言語して大人に伝えていく力が未発達なので、大人側が「本人の思いや願い」を汲み取るためにも、また本人が「自傷や他害」以外の表現手段を身につけるためにも「AAC」の活用が望まれます。
具体的には 「身振りサイン」や「絵カード 、あるいは「YES-NOスイッチ」を用いて本人の意思表示をしやすくしていく様な工夫です。このあたりの対処法は「AAC」と呼ばれる分野なのでが、紙面の都合で詳細はそちらを調べてみてください。 - 「スケジュール・ボード」の活用
お子様が情緒的に不安になる原因の一つに「イレギュラーなスケジュールが入ると時間の流れの予測がつかないので混乱する 」「これから、具体的に何をしていけばよいのかが分からないので不安になる 」という認知機能のつまずきがあります。
これに対して 「TEEACH(ティーチ)プログラム」という自閉性障害がある人たち用の環境構造化システムがありそのアイテムとしての スケジュールボードが使えそうです。
耳で(音声言語だけで)聴いていても情報が流れていってしまうので分かりにくいけど、写真や絵でこれから始まる時間割や、その後何をすればよいのかを視覚的に提示していくことで自閉症の人たちに「見通し」を持って過ごしていってもらう工夫です。
これについても、詳しく語っていくと紙面が溢れてしまいますので別途、その分野の情報を入手しながら、可能な範囲で暮らしの中に取り入れていってください。 - また 今回述べてきた情報だけでは到底語りきれない専門的なお話になりますがお子様が抱えている発達のつまずきの大きな「ウィークポイント」に、中等度の「触覚防衛反応」・・・一般的には「触覚過敏」と言われますが、過敏と鈍感が混在している状態です。
お子様は自閉症のみならず、幼児期前半は中~重度の触覚防衛反応が出ており、それゆえに「愛着形成」が阻害されていた経緯も想像するに難くありません。
この「触覚防衛反応」については、拙著の紹介で恐縮ですが、
「育てにくい子にはわけがある(大月書店)」
「発達が気になる子の感覚統合(学研)」
「発達障害の子の感覚遊び・運動遊び(講談社)」
「発達障害の子を理解して上手に育てる本(小学館)」
「発達障害がある子どもたちの感覚と運動遊びを根気づよくサポートする(日東書院)」
などのの随所に書いておりますので読んでいただければ幸いです。
主として「△△ができない(伸び悩みと言われやすい)」ことについて
Q1. 教わってきた内容が、子どもの発達水準よりも高すぎて理解できていなかった事例
3歳児健診で「知的に遅れがある」ことを指摘され、自治体が運営している発達センターに通い始めました。娘・Iは、小学校にある特別支援学級の年生になりますが、2年生のときから10までの足し算・引き算(2+3や6-2など)を教えてもらっていたのですが、しばらくドリルをさせてないとすぐに忘れてしまいます。知恵遅れってそういうものなのでしょうか?
A1.ポイントは「しばらくドリルでの計算をさせてないと”忘れてしまう”」という点です。はたしてIちゃんの知的障害は「忘れる」ことが問題なのでしょうか?
そうではなく、ほんとうの意味で「数」というものやそれを足したり引いたりす
る思考方法をまだ身につけていないのではないでしょうか?
ご質問を受けた際に、親御さんのお手元にあった「知能検査」の結果報告書を見せていただきました。就学前の年長さんのⅢ学期末、ちょうど6歳になった時に取ったものです。知能指数のことをIQと言いますがIちゃんは「IQ=40」という数字でした。
ちなみに、数字にはすべて「単位」が付くことはご存知でしょうか?もし「IQ」ではなく「体重=」と記されておれば「kg」という単位が付くことが予想されます。「算数のテスト=」ならば「点」というのが単位になるでしょう。では「IQ」にはどの様な単位が付くかを考えてみてください。ほとんどの方が「えっ?」と言葉を止めたり、「点数ではなかったのですか?」と聞き返す方がほとんどです。これは親御さんのみならず、学校の先生方の多くもご存知ない方が多くおられます。
答えは「%」です。パーセントということは「何か」に対しての「割合」です。ここが解れば、この子の発達支援や特別支援教育の一端が見えてくるというものです。つまり「標準発達している子どもの知的水準(平均知能)を基準にした時に、検査を受けた子どもの知能の値が標準の何%か?」を表しているわけなのです。つまり、Iちゃんが年長さんのⅢ学期に知能検査を受けたころの知的な育ち具合は、6歳×40%=2.4歳、つまり2歳代半ば程度の認識力が育っていたわけです。
もちろん知能検査だけで子どもの知的能力の全てが測れるものではなく、IQの値だけが独り歩きする様な支援のあり方は厳に慎まなければなりません。ただ、もしIちゃんの「IQ=40」が正確な値で、数年程度では大きな変動をしていないことを想定すると、Iちゃんは、暦年令が8歳になった小学校2年生のⅢ学期にようやく3.2歳、およそ3歳代前半程度の認識力で足し算や引き算のドリルを習っていたことが推測されます。ここから言えることは、Iちゃんにとっての「2+3」や「6-2」という計算式は、「文字列や記号の羅列」を暗記していた可能性が高いのです。
「学習」していく上で大切なことは「覚える」以上に「理解する」ということです。足し算や引き算の基本は、覚えるものではなく「順序数」や「数量」を理解していくことを土台にしながら、「数量の合成-分解(これが足し算・引き算の原理です)」を具体物で経験しながら頭の中で考えられるように導いていくことなのです。
それでは、どのような指導ができそうなのでしょうか?
ここでは紙面の都合で拙著の紹介で恐縮ですが 「発達障害の子の読み書き遊び・コミュニケーション遊び(講談社)」や「小学校で困ることを減らす親子遊び10(小学館)」にいくつか紹介しておりますので参考にしてください。
担当してる「指導者・支援者」との関わりについて
内容に関しては準備中となります。
その他、子どもの「障害受容」に関わる悩みについて
Q1. 「我が子の発達のつまづき」を受け入れることの困難さについての事例
娘・A子は700g未満の極小未熟児として産まれ、2ヶ月近く新生児集中治療室でのケアを受けて退院してきました。医者からは「必ずしも助かる保証はできない」ことと「たとえ生きれたとしても障害が残る可能性は高いので覚悟するように」とは言われていました。ただ親としては何とか健常に育ってほしくて幼児期から家庭学習を含め学習塾や体操教室などに通わせ懸命に育ててきました。
小学校の1年生の頃はなんとか皆と一緒に学べていたようですが、今年度4年生になるとほぼすべての教科でついていけなくなくなってきました。また最近、円形脱毛症にもなり、平日の朝はなかなか起きてこなくなったり学校から帰ってきても部屋にこもることも増えてきました。しかも、先日の個人面談では、担任の先生からは「支援学級」への転籍を勧められています。せっかく通常学級に通えるように幼少期から頑張って育ててきたのですが、これから娘の進路をどのように考えていけば良いのでしょうか?
就学前から通わせている、発達に遅れのある子向けの学習塾で、6歳の誕生日を迎えた前後の時期に取った発達検査では、運動面でも知能面でも言葉の育ちも全体的に「DQ(発達指数)=75程度」と言われました。また「就学時相談」も受けるように勧められました。しかし、それでは「支援級送り」になるのは間違いなかったのでそれは断わり、今は地元の通常級に通わせています。
A1.このご質問にお答えしていくには、そもそも論としてのキーワードとして、お子様の発達のつまずきに対する「障害受容」というテーマが横たわっています。
そしてこの「障害受容」については、様々な立場で様々なアドバイスがなされており、人によっては「親が子どもの発達のつまずきを認めていないのが問題だ。だからまずは、親が変わらなければならない」というものから 「今の時代、子どもの進路の決定には親の見解が優先されてしまう。その子に対しての必要な対策を実施しようにも、親がガンとして言うこと(転籍など)を受け入れないのだったらどうしようもない」という見解など様々です。
つまり、支援者・指導者の持つ「価値観」によって、その方法は大きく分かれる=「ベストの正解はない」ものであること始めにお断りしておきたいと思います。
その上で、私の見解や判断基準としては
- もともと、親というものは、我が子の発達のつまずきを受け入れる(≒障害を受容する)ことは困難で、受容できるにこしたことはないが「障害受容は親の義務でなない」というところから話しをスタートしていく必要がある。
- 支援の原点は「この子」にとって何が最善か?という発想から出発しなければならないが 「この子」は理想的な環境で生きているわけではなく、他 、でもない「この親」の元でしか生きていけない存在である。
- ならば、いわゆる「虐待」に手を染めている親でない限り 「障害受容できていない親」を丸ごと抱えての支援の方法を考えていく必要がある
というのが私のスタンスです。そこから出発してA子さんの進路について検討してみました。
そこで、まず私が欲しかった情報は、この親御さんが「なぜ、普通学級にこだわり続けてきたのか?」でした。
その理由の1つには、A子さんのご家庭の父方・母方とも親族一同がハイソな仕事(弁護士や医者、大学の教授などの)に就いている一族で、A子さんの「出来の悪さ」が表沙汰にならないようにせざるを得なかったそうです。もし、A子さんが障害児だとなると「どちらの血筋なのだ?」という争いごとになりかネない雰囲気があるとのことです。
しかし、それだけだったら、我が子が円形脱毛症になるまでのストレスにさらす前に、何らかの対策を立てていたはずです。
私は「親の見栄」を一概に否定する気はありません。少なくとも 「見栄」を原動力にしながらも今まで一生懸命にA子さんを育ててきたわけです。この親御さんとの話しを重ねていくうちに見えてきたのが、どうしても「世間体が気になって、支援学級には通わせたくない」この親の心胸でした。親御さんご自身もエリート育ちだったので、両親共々「いつかは普通に戻ってくれる 「それまでの辛抱だ」とふたりで言い聞かせてきたそうでした。
そこで私は、以下の4点を親御さんに提案いたしました。
- とにもかくにも 自分がどれほどの”見栄”を抱えているかを”自覚”すること必要とあらば、カウンセリングも受けること。
- 次に、今までは「A子のために」と言って通わせていた学習塾や普通級について「本当は親が通わせたかっただけなんだ」ということをA子さんに判ってもらうこと。
※親が語る「”あなたのために”△△してあげているのだから」の裏には、本当は親の自己満足(=見栄)が潜んでいることが多いものです。その裏腹さに、子どもは計りしれないストレスを感じるものでしょう。なので「親の本音」を我が子に伝える=我が子にウソをつかない態度が求められるのです。 - その上で、どうしても捨てられない「見栄」ならば、その思いを担任にも伝える努力をしていくこと。
- 最後に、それでもÅ子さんが通常学級での辛さや学習塾に通うことのしんどさを訴えるようならば、そのときは「親の責任」として腹をくくって通常学級での通学を諦めるというものでした。
このケースの結果、および後日談です
まず、親御さんご自身が見て見ぬふりを続けてきた自分たちの「見栄」に向かい合うことで今後の見通しが持てるようになったことは大きかったようです。そして、赤裸々にその思いを我が子と担任の先生に語ったことが契機となり、まずは担任の先生の態度が「A子さんを受け入れる」方向に切り替わり、本人も学習塾は辞めたものの、その後6年生まではストレスフルになることなく「通常学級」に通い続けることになりました。
もちろん、たった一回の話し合いで「見栄」を自覚していくことは困難です。A子さんの「発達支援」のプログラムも実施しながら、1年間ほどの話し合いの結果、前述のなお中学校への進学時は、思い残す(?)ことなく支援学級を選ばれていきました。